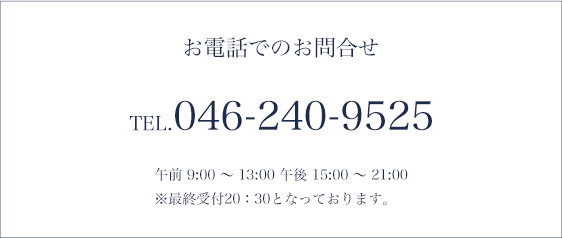背骨の役割
背骨(脊柱)は身体の中心軸として姿勢や運動を支えるだけでなく、自律神経の働きにも深く関わっています。背骨の周囲には交感神経や副交感神経が走行しており、筋肉のこわばりによってこれらの神経が刺激されると、心拍・血圧・呼吸などを調整するバランスが乱れやすくなります。医学的にも、脊柱起立筋や肩甲帯周囲の筋緊張が高まると交感神経が優位になり、体が「戦闘モード」に傾きやすいことが示されています。つまり、背骨周辺の硬さは単なる筋肉の問題にとどまらず、睡眠に必要なリラックス状態を妨げる要因となるのです。
背骨がカタいと…
さらに、背骨の柔軟性が乏しいと呼吸の質にも影響が及びます。胸郭は背骨と肋骨が連動して広がったり縮んだりすることで呼吸が行われますが、背骨が硬く動きが制限されると胸郭の可動性も低下します。結果として浅い呼吸が続き、酸素供給が十分でなくなることは睡眠の質低下と関連することが報告されています。浅い呼吸では副交感神経が優位になりにくく、寝つきが悪くなったり、夜間に何度も目覚めたりする原因にもなります。また、背骨の歪みや硬さは寝姿勢にも影響し、特定の部位に負担がかかることで痛みや不快感を生じ、それが睡眠を妨げる悪循環を生みます。
解決策とは
一方で、背骨の柔軟性を保つことは睡眠改善に役立つと考えられています。例えば、寝る前に軽いストレッチや胸を開くエクササイズを行うことで筋肉の緊張が和らぎ、呼吸が深まり、副交感神経が優位になりやすくなります。医療現場でも、肩こりや腰痛の治療に伴って睡眠の質が改善するケースは少なくありません。背骨の硬さを意識して日常的にケアすることは、特別な治療だけでなく毎日の睡眠環境を整えるうえでも重要です。背骨の柔軟性を高める習慣は、身体的な快適さだけでなく、心身のリラックスを促し、質の高い睡眠へとつながっていくのです。