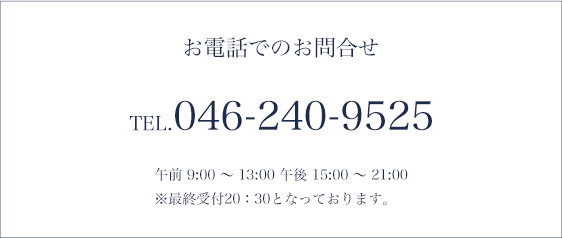肩こりの医学的な仕組み
医学的に見て肩こりとは、首や肩の筋肉が緊張し続け、血流が悪くなることで生じる症状です。筋肉は長時間同じ姿勢が続くと硬くなり、酸素が不足して疲労物質が溜まりやすくなります。その結果、重だるさ、張り、痛みなどが起こります。また、ストレスが強いと交感神経が優位になり、全身の筋肉が緊張しやすくなるため、肩こりが悪化します。本来、首や肩の筋肉は頭の重さを支えながら姿勢を調整していますが、負荷が大きいと筋肉の小さなこぶ(筋硬結)ができ、痛みの原因になることがあります。これらは「筋緊張性の痛み」と呼ばれ、肩こりの中心的な仕組みです。
肩こりを引き起こす主な原因
肩こりの原因として最も多いのは姿勢です。パソコン作業やスマホの使用が長く続くと、顔が前に出た姿勢になりやすく、首の後ろの筋肉に強い負担がかかります。また、猫背や巻き肩になると肩甲骨がうまく動かなくなり、周囲の筋肉がさらに緊張します。加えて、目の疲れ(眼精疲労)は自律神経を介して肩の筋肉を固くしやすく、ストレスや睡眠不足も肩こりを悪化させる要因です。さらに、運動不足で背中や肩甲骨まわりの筋力が弱くなると、首や肩に余計な負荷がかかり、肩こりが慢性化しやすくなります。こうした複数の要因が重なることで、肩こりは長引いたり再発したりします。
予防のセルフケアと対処法
肩こりを予防するには、まず姿勢を整えることが重要です。座るときは、耳・肩・腰が一直線になる姿勢を意識し、パソコンの画面は目の高さに合わせます。また、1時間に1度は立って背伸びをするだけでも血流が改善します。運動としては、肩甲骨を大きく回す体操や、胸を開くストレッチが効果的です。特に、背中の筋肉を使う習慣をつけると肩の負担が軽減します。さらに、入浴や蒸しタオルで温めると筋肉の緊張がゆるみやすくなります。ストレスが強いと肩こりも悪化するので、深呼吸や軽い散歩などでリラックスする時間を作ることも大切です。こうした日々のセルフケアを積み重ねることで、肩こりを大きく予防・改善できます。